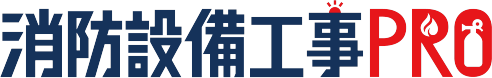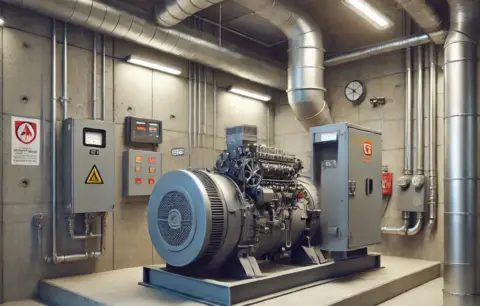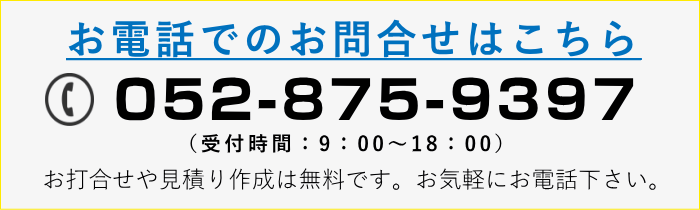避難器具の設置基準
設置基準
避難器具の設置については、防火対象物の全体の規模には関係なく、防火対象物の階の用途とその階の収容人員の数によって決まります。また、用途、設置階などにより設置できる避難器具の種類も決まっています。
どのような防火対象物でも、3階以上の階に収容人員が10人以上で、避難階または地上に直通する階段が2つ以上設けられていない階には、避難器具を設置しなければなりません。用途の2項、3項、16項イの複合用途で2階に2項、3項がある場合は、2階も適用対象となり、これが基本となります。
収容人員が20人以上の6項については、避難器具の設置が必要となり、対象階は地階と2階以上です。収容人員が30人以上の5項についても、設置が必要となり、対象階は地階と2階以上です。5項、6項での避難器具の設置個数は、各階で収容人員が100人以下の場合は避難器具
1個以上、100人を超える場合、更に1個追加となり、それから100人増すごとに1個ずつ追加となります。
収容人員が50人以上の1~4項、7~11項については、設置が必要となり、対象階は地階と2階以上です。避難器具の設置個数は、各階で収容人員が200人以下の場合は避難器具1個以上、200人を超える場合、更に1個追加となり、それから200人増すごとに1個ずつ追加となります。
収容人員が地または無窓階では10人その他では150人以上の12項(工場等)、15項(一般事務所等)については、各階で収容人員が300人以下の場合は避難器具1個以上、300人を超える場合、更に1個追加となり、それから300人増すことに1個追加となります。対象階は、地階と3階以上です。
避難器具の免除
設置対象物の設置個数に対して、対象物の階段が屋外避難階段、特別避難階段または屋内避難階段がある場合、階段の合計数の避難器具の設置個数を免除できます。また、主要構造部が耐火構造で、渡り廊下を設けた場合、渡り廊下のある階は、渡り廊下の数の2倍の避難器具設置個数が免除できます。
また、主要構造部が耐火構造で、開口部には防火戸または鉄製網入りガラスで、2つ以上の直通避難階段が隔たった位置にあり、バルコニーなどを利用して、22以上の異なった経路で直通階段に到達できるような場合、設置自体が免除されます。また、多数階に避難器具を設置する場合、同一直線状にならないように設置します。
避難はしご
避難はしごの種類
金属製避難はしごには、固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしご、ハッチ用つり下げはしごがあり、検定対象品です。避難はしごは、2本以上の縦棒(間隔が内法寸法30〜50cm)に、握り太さが直径14mm以上35mm以下の形または同等の太さの形状の断面の横を隔25~35cmの等間隔で配置をした構造となっています。
固定はしごは、振動または衝撃などによって止め金具などが容易にはずれないような保安措置をし、防火対象物に固定されたはしごです。横桟が縦棒内に収納されて、使用時に横桟が開き使用可能な状態にする収納式もあります。
立てかけはしごは、上部支持点、下部支持点に滑り止めおよび転倒防止のための安全措置を設けたはしごです。
避難はしごの中でも一番よく使われている方式がつり下げはしごです。防火対象物の柱、梁など、または窓枠などで固定をして、使用時につり下げて上から下へ降ろして使用する方式で、足がかりのために壁面から10cm以上の距離を保つような突子が設けられている構造になっています。一般的には、縦棒部が横桟部へ折り畳まれ収納できる折畳式と縦棒部がワイヤーでできており、下部より丸めて収納しておけるワイヤーロープ式があります。また、上部支持部には、窓枠などにかけて固定する自在金具式と手すりゃ固定環などに固定をするナスカンフック式などがあります。
ハッチ用つり下げはしごは、避難器具用ハッチに収納されていて、使用の際、壁面などに突子が接触できない場合に使用されるはしごで、降りる際に揺れにくい構造となっています。
避難はしごの設置
避難はしごを設置する場合、使用に差し支えのない0.5m以上の操作面積が必要です。設置する開口部は、高さ0.8m以上幅0.5m以上または、高さ1m以上幅0.45m以上必要で、開口部を床面に設ける場合は、直径0.5m以上の円が内接できるものとなっています。更に、開口部から地上までの降下空間に架空電線、木、看板、屋根、庇などの障害がないようにしなければなりません。避難はしごの場合、横棒の中心部からそれぞれ外方向に0.2m以上および器具の前面から奥行0.65m以上の角柱形の範囲となります。避難ハッチの場合、ハッチの開口部面積以上となっています。降下した場所で、使用者が避難器具からの離脱あるいは着地してからの体勢を整えるために地上に安全な空地が必要で、避難空地といいます。避難はしごの避難空地は、降下空間の投影面積以上で、安全な道路、広場に通じている場所を選定しなければなりません。
避難用タラップ・避難橋
避難用タラップ
避難用タラップとは、手すりのついた鉄製階段で、避難器具としては地階、2階、3階で使用が可能です。
避難用タラップの構造、材質および強度は、次のようになっています。
安全、確実かつ容易に使用される構造のもので、踏板、手すりなどにより構成されるものです。半固定式のもの(使用時以外は、タラップの下端を持ち上げておくもの)は、一動作で容易に架設できる構造のものとしなければなりません。避難用タラップの手すり間の有効幅は、50cm以上60cm以下で、高さは70cm以上とし、手すり子の間隔は80cm以下となります。踏面には、滑り止めの措置をし、寸法は20cm以上必要で、けあげの寸法は30cm以下とします。踊場は、避難用タラップの高さが4mを超えるものにあっては、高さ4mごとに、踏幅1.2m以上の踊場を設ける必要があります。避難用タラップの材質は、踏板、手すり、手すり子および支持部は、鋼材、アルミニウム材またはこれと同等以上の耐久性を有するものとします。
降下空間は、路面の上方2m以上およでタラップの最大幅員の範囲内とします。
操作面積は、器具を使用するのに必要な広さとし、設置する開口部の大きさは、高さは1.8m以上で、幅は避難用タラップの最大幅以上となっています。
避難橋
建築物相互を連絡する橋状のもので、両端が固定し常時使用できるものと、使用時のみ架設できる移動式のものがあります。
避難橋は、安全、確実、容易に使用される構造のもので、橋げた、床板および手すりなどにより構成されています。避難橋は、安全上十分なかかり長さを有するものであり、移動式のものは、架設後のずれを防止する装置が必要になります。
主要な部分の接合は、溶接、リベット接合またはこれと同等以上の強度を有する接合とします。床板は、勾配を1/5末満とし、すべり止めの措置をし、すき間の生じない構造、床板と幅木とは隙間を設けないものとします。手すりなどは、避難橋の床板などの両側に取付け、高さは1.1m以上、手すり子の間隔は18cm以下、幅木の高さは18cm以上必要です。手すりと床板との中間部に、転落防止のための措置をする必要があります。材質は、構造耐力上主要な部分を不燃性のものとし、橋げた、床板、幅木および手すりは鋼材、アルミニウム材またはこれと同等以上の耐久性を有するものを使用します。積載荷重は3.3kN/mで、たわみは支持間隔の1/300を超えないようにする必要があります。
緩降機
緩降機の構成
緩降機は、使用者が他人の力を借りすに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構で調速器、調速器の連結部、ロープおよび着用具で構成されています。常時取付け具に固定されて使用する固定式と、使用時に取付け具に取付けて使用する可搬式があります。
固定式は、常時取付け具に固定されているため、調速器を取付金具に取付ける手間が省けます。可搬式は、一般に収納した時の見た目が固定式に比べて良好です。調速器は、緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置で滑車、歯車、遠心ブレーキで構成されており、安全に降りることができるように、降下速度を調軽します。ロープが動くと滑車軸に連動した歯車が回転し、その回転が速まると遠心ブレーキが働いて、加速度をゼロに保ちます。このため、緩降機は体重や降下距離にかかわらず一定の速度で降下することができ、着地時のショックもありません。取付け具と調速器を連結する部分を調速器の連結部といいます。着用具は、使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具で、一部が輪状になっており、中に入っているスプリングによって装着した後の着用具のすれ落ちを防ぎます。また輪になった部分はクッションがついていますので、降下時の避難者のベルトによる圧迫を防ぎます。緊結金具は、ロープと着用具を連結する会具です。リールは、ロープおよび着用を収納するために巻き取る用具で、梅産製は投げ降ろした時に人に当たってもな全なように軽量化されていて、二次災害を防ぐため転がらないような形状になっています。
緩降機は降下の際、ロープが防火対象物と接触しないように、壁面から15~30cm離れた場所になるように取付け金具を設置します。ロープの長さは、取付け置から出盤直の降着面までの長さとします。操作面積は、0.5m以上で、1辺の長さは各々 0.6m以上とします。降下空間は、器具を中心とした半径0.5mの円形柱の範囲内とします。避難空地は降下空間の投影面積です。
緩降機の使用方法
緩降機の使用方法は、建物の床・壁にアンカーボルトなどで固定されている取付け金具をセットします。ロープの巻いているリールを外へ落とし、その後、もう一方の着用具を装着します。着用具の装着は、避難者が着用具の輪になった部分に体を通し、脇から胸元あたりへくるように装着します。2本のロープを持つて外へ出て、体を壁面に向けてロープをはなし降下をします。降下とともに、先に下へ落としていたもう一方の装着部か上の調速機の方へ上がり、交互に1人ずつ降下できるようになります。